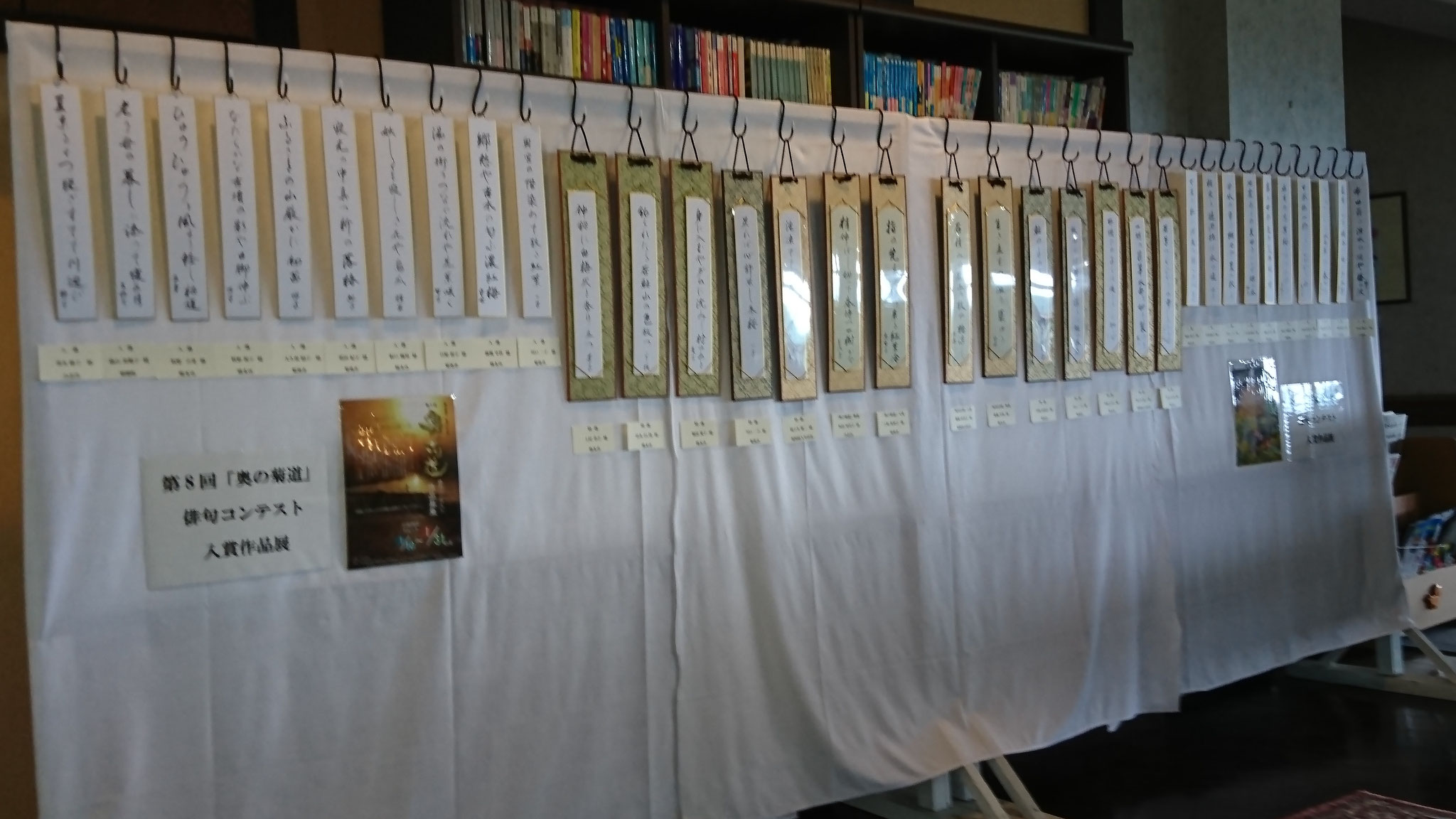「奥の菊道」俳句コンテスト
「奥の菊道」俳句コンテストは
これから少しずつ消えていってしまうかもしれない
美しい自然の風景や懐かしい生活が残る
熊本県内の故郷の情景を俳句に詠んでいただき
その俳句を広くご紹介していくことで
大切なことを見失ってしまった現代の日本社会への
故郷からの最後のメッセージを伝えていくことを
目的とした俳句コンテストです。
熊本県内の故郷に吟行いただき、そこで詠まれた皆様の俳句を
「奥の菊道」俳句コンテストにご応募ください。
このホームページの「心の旅」に掲載されている俳句は
過去12回の「奥の菊道」俳句コンテストの入賞作品と
「奥の菊道」通信俳句会の優秀作品です。
一句一句の俳句を読み進めていただければ、
素敵な心の旅のお時間になることでしょう。